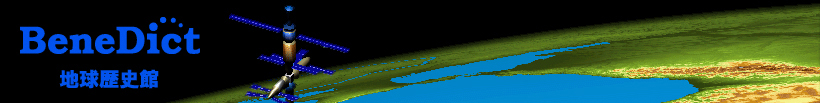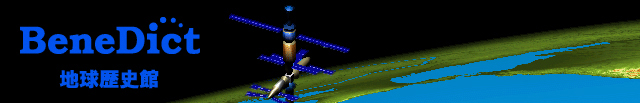■開村800年の天領 2020.02.02
仕事が大忙しで、テンパっていると、実家から電話があった。
「新宅のお父さんが亡くなったので、すぐに行かれたし」
両親が高齢で弱っているので、僕が代理とのこと。
通夜か葬儀だと思ったら、葬儀の打ち合わせだった。
葬儀の打ち合わせ?
僕が?
何についた話?
そもそも、「新宅」って何?
わからないことだらけだ。そういえば、仕事にかまけて、親戚付き合いは両親に任せっきりだった。また、母から「長男の自覚がない!」と説教されるのがメンドーなので、すぐに飛んで帰った。
まず、実家で情報収集。「新宅」とは分家のことらしい。実家の4代前、つまり、ひいひいじいさんの代に、分家したらしい。うちは本家なので、分家の葬儀を仕切るのだという。
はぁ?ムリですよ!
村のしきたりなんて、ゼンゼンわかりませんから~
すると、母は呆れた顔でこう言った。
「お前はあてにならないから、本家に頼んでおいた。本家のあんちゃんのそばで、黙って座っていればいいよ」
つまりこうこと。
亡くなったのは、わが家の分家の当主。葬儀を仕切るのは、わが家の本家の当主。なんか、ややこしい。
これまで暮らした東京や金沢では、冠婚葬祭を仕切るのは親か子か親しい親族。ところが、田舎では、本家が仕切るらしい。
若い頃、こんな田舎のしきたりがイヤで、高校卒業と同時に実家を出た。だから、4代前の親戚なんか知るわけない。とはいえ、両親が高齢なので、少しづつ覚えていくしかない。知らぬ存ぜずを決め込んでいると、あいつは長男のくせに、親戚の名前も覚えられん、アホやぞ、今の代でおわりや、なんて心ない風評が立つのがみえている。
というわけで、葬儀の段取りでは、母の言いつけどおり、本家の当主に張り付いて、黙して語らず。葬儀の後の会食では、一転、これでもか愛想を振りまいた。後で、母に告げ口されてはたまらないから。
とはいえ、前も、斜め前も、横も、じいさんとばあさんばかり。世代が違うし、一族のことも知らないので、話題が作れない。ところが、ありがたいことに、年寄りは話し好きだ。向こうから、話題をふってくれた。そのほとんどが、一族と村の話なのだが、これが存外面白い。
実家のある村は、加賀と能登の境界に位置する。県庁所在地の金沢から40kmほどの距離だ。193軒しかない寒村だが、江戸時代、天領だったという。
天領とは、江戸幕府の直轄領である。日本全国に分散し、田畑、交通や商業の要衝、港湾、鉱山や山林を基準に選ばれた。
興味深いのは、実家の村は天領なのに、周囲の村はすべて加賀藩領。つまり、広大な加賀藩領の中に、わが村がポツン。完全に孤立している。
加賀藩は、江戸時代屈指の大名家で、加賀100万石として知られる。織田信長の家臣、前田利家が創設した。首府は今の金沢で、北陸新幹線が開通した後、観光客でにぎわっている。
ところで、実家の村は、なぜ、天領になったのだろう?
領地は狭く、土地は砂地で痩せている。山林はこじんまりで、商業地も港もない。年寄りたちが言うには、交通の要衝だったからだという。たしかに、古い地図で確認すると、この村は、2つの重要なルートの交差点にある。江戸から越後経由で加賀に至るルートと、加賀から能登に抜けるルートだ。ちなみに、石川県は能登と加賀からなる。だから、わが村は交通の要衝だった?たった193軒の村に、JRの駅があるのは、そのなごりだろうか。
「交通の要衝」説の根拠がもう一つある。
江戸時代、輸送業者には縄張りがあり、リレーの要領で物資が運ばれた。ところが、効率が悪く、輸送業者のうまみも減る。そこで、わが村の輸送業者は、加賀と能登の境界という地の利を活かして、輸送ルートを独占しようとした。それを加賀藩に直訴したところ、特例として認められたという。
なぜか?
加賀藩は100万石を誇ったが、外様大名だった。幕府が、加賀藩の取り潰しをもくろんでいたことは衆知だ。そんな状況で、天領のわが村に、告げ口されたくない。だから、虫のいい直訴をのまざるをえなかった・・・
年寄りの仮説にすぎないが、辻つまはあっている。
天領の恩恵はもう一つあった。
この村は、周囲の加賀藩領より、暮らしぶりが良かったという。加賀藩領の村民は、加賀藩の過酷な搾取で苦しんでいた。一方、わが村の領主は、遠く離れた江戸幕府。目が届かず、しめつけがゆるかったのだろう。
この村は、今年、開村800年を迎える。逆算すると、開村は1220年頃。鎌倉時代の「承久の乱」と一致する。あくまで仮説が、開村はこの乱と関係があるかもしれない。
承久の乱は、武家が朝廷を武力で倒した史上初の事件だった。後鳥羽上皇が、鎌倉幕府執権の北条義時に討伐の兵を挙げ、敗れたのだ。この戦いで、幕府側の北条朝時が一軍を率いて、「鎌倉→越後国→わが村→加賀国→京」のルートで進軍している。つまり、わが村は、加賀国と越後国の国境に位置する。幕府軍が進軍する際、交通の要衝、補給基地として、この村を開いたのかもしれない。
村の開祖もわかっている。姓は「松永」で、村の長として、400年間この村を支配したという。ところが、江戸幕府が開かれると、村は天領になり、幕府側の農民が入植してきた。それが、わが家の本家だという。その後、わが本家と松永氏は対立と婚姻を繰り返しながら、この村の支配し続けた。農民でありながら、帯刀も許されたらしい。そして、今から200年前に、本家から分家したのが、わが家なのだという。というわけで、貧しい農民にも、誇るべきルーツがあるわけだ。
最後に、わが家の本家に伝わる話。
曹洞宗といえば、言わずと知れた、日本の禅宗の一派。その中興の祖が、若い頃、実家の村でおいはぎをしていたというのだ。その後、曹洞宗に入門、改心して、法嗣(継承者)までのぼりつめたという。日本が食うや食わずの時代、「レ・ミゼラブル」のジャン・バルジャンを彷彿させるではないか。その記録文書が、本家に残っていたが、先々代のときに、消失したという。
やはり、歴史は面白い。
誰もが知る歴史イベントと、身近な記録がつながると、歴史の厚みが増す。本当に面白い歴史とは、このような「つながり」をいうのだろう。
by R.B