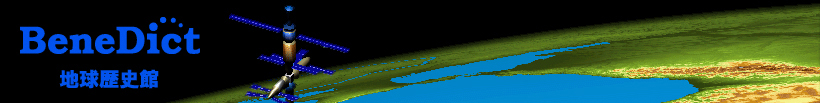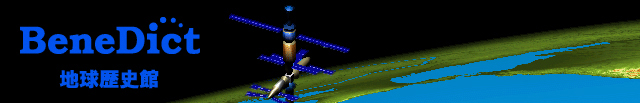人間とネコとAIの知能(2)~冥界の同伴者~
■神を警護するネコ
愛くるしいだけがとりえのネコ。
ネズミ捕りの武勇伝も、遠い昔の話・・・今は役立たず、とライバルのイヌは見抜いている。
ところがどっこい、ネコは頂点捕食者だ。
どういうこと?
食物連鎖の頂点に立つ人間が、ネコを守っているから。つまり、天敵がいない。
それどころか、ネコは、人間に巧みに取り入って、寝床付き、食事付き、遊び相手付きの優雅な生活をおくっている。ネコの先祖は山猫で、自給自足できるのに。
人間の一方的な奉仕にみえるけど「猫の恩返し」は?
一緒にいてくれるだけ。
人間は気づいていないのだ。人間がネコを飼っているのではなく、ネコに飼われていることを。イヌはそれに気づき、不満に思っているが、人間に忠実なので、いつも尻尾をふっている。もちろん、ネコはご機嫌取りなど無縁だ。
ネコは人間の上なの?
そうなのだが、上には上がある。古代エジプトだ。
紀元前1900年頃の上エジプトの墓地で、小さな墓が見つかった。17匹のネコの骨が埋葬され、そのそばに、小さな壺が並べられていた。ネコの好物の牛乳が入っていたと推定されている。
ネコが、人間以上に手厚く葬られていたことは間違いない。
時代は進み、紀元前1000年以降、ネコは神の顕現(けんげん)になった。神の顕現とは、神が人前に姿をあらわす際の化身である。
その象徴が女神バステトだ。エジプトの最高神ラーの娘で、人を罰する役目をにない、「ラーの目」と恐れられた。女神バステトは、頭がネコ、身体が人間の姿で描かれている。
さらに、発掘された王家の墓には、こんな絵が描かれていた。

夜、冥界を通り抜けていく太陽神ラーを警護するネコ。ラーが冥界の旅から帰還し、最後の門で番をするのもネコだ。ネコは、神の守護者だったのである。
古代エジプト人にとって重要な「死者の書」にも、ネコは登場する。死者の書はパピルスの巻物で、死者とともに葬られた。不吉な響きがあるが、大当たり。死者の書には、埋葬の儀式が書かれていたのだ。その中には、不穏な文言も含まれる。死者の魂が、冥界の危険な旅を終えて、死後の世界に入るときに唱える呪文だ。
それだけではない。神の敵に目を光らせるネコも描かれていた。
神の敵に目を光らせる・・・これにはリアルな根拠がある。
ネコの目は、本当に光るのだ。
暗闇で、ネコに光をあてると、目がキラリと光る。秘密の霊力があるからではない。ネコの目の奥には、タペタム・ルシダムという特殊な反射板があり、これに光が反射して、目が光るのだ。
それが?
この仕掛けのおかげで、ネコは暗闇でもよく見える。
カラクリはこうだ。
一度通過した光が、タペタム・ルシダムで反射して、もう一度網膜に当たるので、光量が増える。望遠鏡は、口径が大きいほど光量が多く、解像度があがるのと同じだ。さらに、目に桿体(かんたい)細胞とよばれる光を感知する細胞がたくさんある。つまり、ネコはわずかな光を最大限に利用できるように進化したのだ。
ネコに限らず、夜行性動物の目が光るのは、すべてこれ。
■冥界の同伴者
古代エジプト人はこう信じていた。
ネコは目を光らせて、神を守護するだけではなく、人間も守ってくれると。
物的証拠がある。
神のそばに寄り添い、神を支え、守護するネコの肖像が残っている。さらに、人間がネコの前にひれ伏している像もある。
とはいえ、像は持ち運びに不便なので、人々は、ネコをかたとった黄金の護符を身につけた。
家が火事になると、住人は財産よりもネコのことを心配したという。大きな声ではいえないが、家族より心配だったのかもしれない。
そして、きめつけはミイラだ。
古代エジプト人は、死後も人生は続くと信じていた。死後の世界へ行くときには、いくつかのアイテムを持っていく必要がある。遺体もその一つだ。そこで、遺体が腐らないようにミイラにしたのである。
ミイラ作りは難しい。そのため、エンバーマーと呼ばれる特別な神官が製作した。
まず、遺体から内蔵を取り出し、乾燥させて、カノプス壺と呼ばれる容器に入れる。脳も取りのぞいたが、心臓は残した。古代エジプト人は、心臓に魂があると信じていたのだ。内蔵を取り出した後、遺体にナトロンと呼ばれる特殊な塩を詰めて乾燥させる。その後、布とおがくずを詰めて、作り物の眼を入れて細長い布でくるんだ。こうして出来上がったミイラは、サルコファガスと呼ばれる棺に収められ、墓所に置かれた(※1)。
全工程は70日にもおよんだが、これはファラオのミイラで、最高品質。貴族や神官のミイラは品質が落ちた。富裕市民はさらに品質が落ち、庶民にいたっては砂漠で自然乾燥。これをミイラとよんでいいものか、まぁ、そこはドーデモいい。そして、貧困層はミイラにしてもらえなかった。
ところが、古代エジプトでは、ネコのミイラも作られたのだ。
紀元前4世紀、ヘルモポリスの大共同墓地にそばに、ネコの大墓地がつくられ、ネコのミイラが埋葬された。近くに、ネコの立派な寺院があり、その特別の飼育所で、ネコは育てられた。
ネコと庶民とどっちが上?
ところが、庶民がそれに不満をもって、暴動をおこした形跡はない。
それどころか、庶民もネコに絶大な信頼を寄せていたのだ。
古代エジプト人は、死生観が強く、死をめぐる観念に支配されていた。
一方、ネコは、死を知らないから、死を怖れない。ネコは「生の肯定者」であり、その魂は不死である。
人間が、死んだ後、冥界を通り抜ける旅では、ネコに同行してほしいと願うのは当然だろう。
■エジプトのネコとミノアのイルカ
動物の神格化は、エジプト文明だけではない。
エジプト文明と交流があったミノア文明でも確認されている。
ミノア文明は、ヨーロッパ最古の文明だ。中心は、エーゲ海に浮かぶクレタ島のクノッソス宮殿で、クレタ文明ともいわれる。
クノッソス宮殿は、牛頭人身の怪物ミノタウロスと迷宮、アリアドネの糸、イカロスの翼など、多くのエピソードで彩られている。
華やかで、ワクワクする物語だが、フィクションとは言い切れない。
というのも、まず、クノッソス宮殿は実在した。
1900年、イギリスの考古学者アーサー・エヴァンズが発掘したのだ。その遺跡から、1000を超える部屋、迷路(ラビリンス)があったと推定されている。ただし、牛頭人身の遺体は確認されていない。
一方、クノッソス宮殿は謎が多い。
怖い説がある。
世界史の授業では、ミノア文明は開放的で明るい海洋文明で、クノッソス宮殿は王宮だったと習う。ところが、クノッソス宮殿は霊廟だったというのだ。
提唱者のH・G・ヴンダリーヒは「迷宮に死者は住む」で、身の毛もよだつ論説を展開している(※2)。
まず、王が住む宮殿なのに、外敵を防ぐ城壁がない。また、王宮の入口が凶とされる西の方角にあるのもおかしい。日が昇る東の方角は「誕生と再生」を表し、日が沈む西の方角は「死と黄泉の世界」の象徴だからだ。
もし、クノッソス宮殿が霊廟、死者の世界だったとしたら、墓場に防衛壁はいらないし、入口は「死と黄泉の世界=西の方角」にあって当然だ。
さらに、建物の内部が石こうで固められていた。石こうは、軟らかく傷つきやすいので、人間の居住区には適さない。
もし、「生きて動き回る者」がいないとしたら、壁に傷がつくことはない。
もっとおかしなことがある。浴槽らしきものがあるのだが、小さすぎて、人が入れない。
もし、死者をポッキリ折って納める棺(ひつぎ)と考えれば問題ない。
くわしくは・・・クノッソス宮殿に死者は住む ~クレタ島の謎~。
話をもどそう。
そのクノッソス宮殿の中に、イルカが描かれた陶棺が見つかっている。ミノア文明では、イルカは死者の魂を彼岸へ導く動物とされたのだ。
ミノア文明とエジプト文明で「死者の魂を導く動物」の概念が共有されていた?
というのも、ミノア文明は、紀元前2000年から紀元前1600年頃に栄えた。一方、古代エジプトで最初に死者の書が作られたのは、紀元前1700年頃。つまり、時期が一致する。
さらに、ミノア文明とエジプト文明が交易していたことがわかっている。クレタ産の陶器がエジプトで出土され、エジプト産のスカラベや象牙がクレタ島で発見されたからだ。交易があれば、概念の交流もあっても不思議ではない。
ただし、エジプトのネコと、ミノアのイルカの存在意義はビミョーに違う。
クレタのイルカは「死の肯定」である。死を受け入れて、自然に、死者の魂を彼岸へと導く。
一方、エジプトのネコは「生の肯定」である。現世と来世はシームレスであり、死んだ後も、生者のように扱い、死の領域を安全に通過し、彼岸へと導くのである。
■ネコの起源
人間のネコ愛は、古代エジプトから現代まで続く。
では、ネコと人間と共棲は、いつどこで始まったのだろう?
現在、家の内外をとわず、人間社会で暮らすネコを「イエネコ」とよんでいる。つまり、野良ネコもイエネコである。
イエネコの大先祖は、食肉目ネコ科に属する山猫で、その中のフェリス・シルヴェストリス(ヨーロッパ・ヤマネコ)というたった1種類のネコが、人間と共棲する術を身につけた。その一種、フェリス・シルヴェストリス・リビカ(リビアヤマネコ)の子孫が、イエネコなのである。
リビアヤマネコは、約13万1000年前、北アフリカから中東、西アジアに生息していた。現在も、赤道以北のアフリカと、アラビア半島からカスピ海にかけて分布している。
リビアヤマネコは、見た目はイエネコとかわらない。サイズは中型ネコで、柄模様はキジトラネコに似ている。警戒心が弱く、懐きやすいが、日本では、許可なく飼うことはできない。ネコは、肉食100%の捕食者であることをお忘れなく。
では、リビアヤマネコは、いつどこで、イエネコになったのだろう?
紀元前4000年頃、リビアヤマネコがエジプトの集落にやってきた。
そして、穀物倉庫を荒らしまわっていたネズミやヘビを食べはじめた。ただし、穀物には手をつけない。100%肉食だからだ。穀物を守ってくれるので、人間はネコに感謝感謝、ネコは安定的に食料(ネズミ・ヘビ)にありつけるのでハッピー。
こうして、ネコと人間の共棲がはじまった。紀元前2000年頃には、ネコは人間社会にすっかりとけこんだ。これがイエネコの起源である。
その1000年後、ネコは、古代エジプトで神になったのである。
一方、ネコのライバルのイヌは一足早く、人間社会に入り込んでいた。1万5000年前から人間と共棲していたらしい。
ネコはネズミ捕り、イヌは番犬からはじまり、人間の信頼を勝ち得たのだが、存在意義が少し違う。
イヌは、飼い主をみると、尻尾をふって、愛想を振りまく。正真正銘の愛玩動物だ。
だが、ネコは違う。
ネコは飼い主に媚びないし、そもそも人間を飼い主とも思っていない。一説によると、ネコは人間を「でかいネコ」と思っているらしい。
寝食を与えられているのに、ネコは人間を主人とは思っていない。こんな恩知らずのネコが、人間の大事なパートナーになったのだ。いや、パートナーどころではない。人間を超越し、神の領域に入ったのだ。
というわけで、人間とネコの共棲の始まりは、4000年前のエジプトが通説である。
ところが、歴史の「最古」はあてにならない。1日でも古いものが発見されたら、大逆転だ。
それが、イエネコでもおこったのである。
考古学的、遺伝学的発見がすすんだおかげで、イエネコの起源が更新されたのである。
■ネコの地球征服
東地中海のキプロス島に、シクロカンボスという村がある。
9500年前の新石器時代の遺跡で、そこで墓が見つかった。墓の中には、人間の遺体があり、すぐそばに、生後8ヶ月のネコが骨がみつかった。人間でいうと12才ぐらいで、人間といっしょに埋葬されたのだから、家族同然だったのだろう。
こうして、イエネコの起源は、4000年前のエジプトから、9500年前のキプロス島に更新された。
じつは、この発見は、もっと大きな意味がある。
イエネコは、キプロス島原産でないし、海も泳げないから、人間といっしょに船で渡ってきたのだ。イエネコの先祖リビアヤマネコは中東にいたから、そのあたりからやってきたのだろう。直線距離で100kmなので、この時代の船でも射程距離内だ。
つまり、ネコは1万年前から、人間に連れ添って旅をしていたのだ。
さらに、興味深いデータがある。
世界規模で、ネコのDNAを調査したところ、人類が世界中を旅するのに合わせて、ネコたちもいっしょに航海していたことが判明した。船旅では、ネコは食料をネズミから守り、船乗りたちを癒やしてくれただろう。やがて、ネコを乗せない航海は不吉と見なされるまでになった(※3)。
つまりこういうこと。
ネコは人間といっしょに、世界中を旅し、あらゆる土地に住み着いた。ネコは人間に連れ添って、世界を征服したのである。
では、ネコはいつ日本にやって来たのだろう。
弥生時代に、すでにネコが飼われていたらしい。長崎県壱岐市にある弥生時代のカラカミ遺跡から、1~3世紀のネコの骨が発見されたのだ(※3)。卑弥呼の時代に、ネコが地球を半周し、日本に上陸していたのだ。
ここでネコと人間のつながりを総括しよう。
ネコは1万年前から、人間と共棲していた。さらに、3000年前のエジプトでは、ネコは神になった。そして、21世紀の現代では、人間に身を守らせて、頂点捕食者になっている。
知能とは、環境に適応し、生き残る能力である。
よって、「生き残り」視点でみれば、ネコの知能は人間と同等?
理屈の上では、そうなる。
知能には、IQと賢さがある。
人間は前者だ。読み書きソロバンで、恐ろしい武器をこさえて、最強の頂点捕食者にのぼりつめた。
一方、ゴキブリは頂点捕食者ではないが、約2億年も生き残っている。原因は「賢さ知能」にある。全身に神経節(ガングリオン)を張り巡らし、分散型脳を構築している。そのため、頭を切り落とされても、身体は動く。しかも、なにかおこると、0.03秒以内に全身で反応できる。すべて、ゴキブリのムダ・ムラ・ムリのない賢い脳のおかげ。
では、ネコは?
読み書きソロバンはムリなので、ゴキブリと同じ「賢さ知能」。
ところが、ゴキブリと違い、最強の人間を家来にしているから、もっと賢い?
人間は高いIQと抽象的思考力を駆使して、小難しい哲学を創り上げた。それで、他の生物を上から目線で、自分たちが上等だと思っている。ところが、ネコには通用しない。ネコは、人間を奉仕者、底の浅いご機嫌取りぐらいにしか思っていない。
ひょっとして、ネコ式知能は人間式知能より上?
そこで、知能視点で、人間とネコを比較してみよう、ついでにAIもからめて。
面白い展開になりそうだ。
参考文献:
(※1)138億年のものがたり 宇宙と地球でこれまでに起きたこと全史 クリストファー・ロイド (著), 野中 香方子 (翻訳) 出版社:文藝春秋
(※2)H・G・ヴンダリーヒ「迷宮に死者は住む」新潮社
(※3)ネコ全史 君たちはなぜそんなに愛されるのか (ナショナル ジオグラフィック別冊) ナショナル ジオグラフィック (編集)出版社:日経ナショナル ジオグラフィック
(※4)猫に学ぶ――いかに良く生きるか ジョン・グレイ (著), 鈴木晶 (翻訳)出版社:みすず書房
by R.B