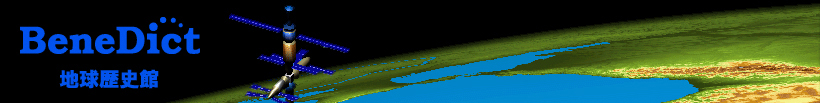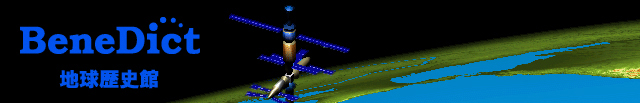人類はネアンデルタール人を滅ぼしたか?
■人間は考える葦か?
早熟の天才パスカルは、こんな名言を残した。
人間は考える葦(アシ)である。
葦はイネ科の多年草で、異様に細長い。そのため「弱い」代名詞とされ、この格言も、人間は葦のように弱いが、考えることで偉大になれたという意味。
それがドーシタ、なのだが、偉人が言うと、名言になるわけだ。
とはいえ、この喩えは、パスカルの格言以外にみたことがない。普遍的な比喩かどうか怪しいので、使うときは注意しましょう。
偉大なパスカルをディスるつもりはないが、この格言は大事なことを忘れている。考えるだけでは、頂点に立てないこと。そう、食物連鎖の話だ。地球が誕生した46億年前から現在まで、弱肉強食バトルは続いている。
2025年時点で、頂点捕食者は人類だが、これまでに遭遇した最大のライバルはネアンデルタール人だろう。
ネアンデルタール人は、ホモ・サピエンス(現生人類)と同じヒト属に属し、同時期を生きた。しかも、分布範囲が非常に広い。かつて、西ヨーロッパを中心に、中東から中央アジア西方までとされたが、今は、シベリア、中国雲南省まで拡大している。新たな物的証拠が見つかったのだ。
ところが、4万年前、あっけなく滅ぶ。
何があったのか?
生息域が広大なので、局所的な事件で”絶滅”したとは考えにくい。一方、地球規模の大災害で絶滅した可能性も低い。同時期、世界中に分布していたホモ・サピエンスは生き残っているから。
というわけで、最も可能性が高いのはジェノサイドだ。
ネアンデルタール人の集団は小さく、広く点在していた。それを根絶するには、きめ細かな、しらみ潰しの地上作戦が欠かせない。そんな徹底した悪事をやらかすのは・・・ネアンデルタール人と生息域を共有し、かつずる賢い生物種・・・そう、ホモ・サピエンス、つまり、われわれ人類である。
この種族の性の悪さは折り紙付きだ。ジェノサイドのみならず、いろんなうしろめたい黒歴史を隠し持っている。
ホモ・サピエンスの起源は、長い間、30万年前のアフリカ東部とされてきた。ところが、その説は2017年に覆された。1960年代にモロッコのジェベル・イルードで発見された35万年前の化石が、初期のホモ・サピエンスと同定されたのだ。というわけで、2025年時点で、ホモ・サピエンスの起源は、35万年前のアフリカ北部。
一方、ネアンデルタール人が出現したのは、40万年前頃と推定されている。ホモ・サピエンスより少し早いが、ほぼ同時期と考えていいだろう。
ネアンデルタール人は「旧人類」と蔑まれているが、「現生人類」のホモ・サピエンスに大きく劣っていたわけではない。
そもそも外見からしてかわらない。めかし込んで街を歩いていたら、それとは気づかないだろう。
外見だけではなく、知能も大差がなかった。
衣服や道具をこさえ、火をおこし、煮たり焼いたり、高度な燻製の技術ももっていた。さらに、いかつい外見に似合わず、優しい性質だったらしい。骨折したあと、長生きした骨がみつかっているからだ。病気やケガを負った者がケアされる社会だったのだろう。われわれは「現生人類」と威張っているが、働かざるもの食うべからず的発想は、昔も今も存在する。
ネアンデルタール人は、死者を埋葬した痕跡がある。さらに、宗教が存在した可能性も。つまり、「旧人類」は、高い知能の目安となる「抽象的概念」をもっていたのだ。
そして、驚くなかれ、ネアンデルタール人は言葉を話していたという。
根拠は3つある。
発声に必要な舌骨をもっていた。
言語習得に有利になFOXP2遺伝子をもっていた。
脳に言語処理に必要なブローカ野やウェルニッケ野があった。
それなら、言葉が話せないほうがおかしい。生物学的に備わっている「話す」機能を、40万年も使わないのは不自然だから。目、耳、指、腕、脚は、種が誕生したときから使っていたのだ。
つまりこういうこと。
旧人類・ネアンデルタール人は、現生人類・ホモ・サピエンスと大差はなかった。少なくとも滅亡した4万年前までは。
■人間は文字を使う葦である
ではなぜ、ネアンデルタール人はホモ・サピエンスに滅ぼされたのか?
この2つの種族は、酷似しているが、大きな違いがあった。
文字である。
ホモ・サピエンスは文字を獲得し、ネアンデルタール人は最後まで獲得できなかった。
では、ホモ・サピエンスが勝利したのは文字のおかげ?
半分正しいが、半分間違っている。
まず、「半分正しい」から。
文字を使えば、生存競争で有利になる。
理由は2つ。
第一に、道具の進歩が早い。
文字があれば、知恵と知識を共有し、継承できるので、蓄積的進歩が可能になる。結果、優れた武器も生まれるから、戦いも有利だ。
第二に、集団が大きくなる。
文字があれば、大きな集団を維持できる。決まり事を集団に周知徹底させるには、口承より文書の方が効率がいい。口承は音なので、伝えた瞬間、消滅する。ところが、文書は時間と空間を超越している。そして、集団が大きいほど、動員兵数が増え、戦いが有利になる。
実際、ホモ・サピエンスの集団は、ネアンデルタール人よりはるかに大きかった。
では、「半分間違い」は?
ネアンデルタール人の滅亡は4万年前、ホモ・サピエンスの文字の発明は5000年前。ネアンデルタール人が滅んだ後で、文字が発明されたわけだ。よって、文字の発明は滅亡の原因にはならない。
ただ、不思議なことがある。
ホモ・サピエンスは誕生してから99%の期間、文字をもたなかったのだ。35万年の間、文字に気づかなったわけだ。
ところが、文字を使い始めると、残り1%の期間で、一気に文明を開花させる。
文字は、気づくまで時間がかかるけど、使いだすと文明爆発を引き起こすわけだ。
それで、気になることが。
最新AIの「大規模言語モデル(LLM)」は、人間より巧みに言葉を操るけど、人類大丈夫?
そして、ここからは妄想です。
もし、ネアンデルタール人が現代まで生き延びていたら、文字を発明していたかもしれない。
ホモ・サピエンスは、35万年かけてやっと文字を発明した。それなら、ネアンデルタール人の生存期間は36万年なので、もうちょっとだったかも。
そんなもう一つの世界を妄想する。
ホモ・サピエンスとネアンデルタール人は共存したのだろうか、それともジェノサイド?
性悪なホモ・サピエンスのことだから、後者だろう。核兵器を使用したかどうかわからないが。
ここで、一度整理しよう。
ホモ・サピエンスもネアンデルタール人も、4万年前までは、大差なかった。しかも、この2つのヒト属は交配していたらしい。現在の人類のDNAに、ネアンデルタール人のDNAが1~4%混ざっているから。ただし、アフリカ人は0%なので、ネアンデルタール人はアフリカにはいなかったのだろう。
つまり、人類の最終決戦は「ヨーロッパ産のネアンデルタール人 Vs. アフリカ産のホモ・サピエンス」だったのだ。
そして、4万年前、ネアンデルタール人は敗北する。その後、ホモ・サピエンスは、文字を発明し、現代の驚異的な文明を築いたのである。
つまりこういうこと。
人間を偉大ならしめたのは「考える」ではなく「文字を使う」。考えるだけなら、ネコでもできるので。パスカルの文脈でいうと、「人間は考える葦」というより「人間は文字を使う葦」なのである。
それでも、パスカルを尊敬していることを付け加えておきますね。
■パピルスおじさん
文字の発明は、現生人類(ホモ・サピエンス)を食物連鎖の頂点に押しあげた。
だが、謎もある。
文字の発明が、世界でほぼ同時期だったこと。
四大文明で確認しよう。
シュメール文明は、紀元前3200年頃(楔形文字)。
エジプト文明は、紀元前3100年頃(ヒエログリフ)。
インダス文明は、紀元前2600年頃(インダス文字)。
黄河文明は、紀元前1300年頃(甲骨文字)。
シュメール文明とエジプト文明に、本格的な交易はなかったが、ゆるい物品交換はあったようだ。エジプトの墓にシュメールの円筒印章が、シュメールの遺跡にナイル産の工芸品の見つかっているからだ。
一方、シュメール文明とインダス文明は、活発な交易があったらしい。シュメールに、インダスの印章や貴石カーネリアンが、インダスに、シュメールの楔形文字の記録、毛織物、青銅器が見つかっているから。
数千年前、あのシュメール文明とインダス文明が海上交易をしていた!?
考えるだけで、ワクワクするが、まともな文献は存在しない。地中海からインド洋の古代交易といえば、蔀勇造の「エリュトラー海案内記」が有名だが、この二大文明の交易には触れていない。この書は 1世紀の話で、二大文明とは3000年も違うのでしかたがないか。
それはさておき、交易があれば、文字が伝わってもおかしくない。
ところが、この三文明の文字に共通点はない。
エジプト文字は絵文字だし、シュメール文字は楔形文字で、インダス文字はそもそも未解読だ。
さらに、文字の媒体も違う。
シュメールは粘土板で、エジプトはパピルス、インダスは焼いた石(ステアタイト)で、粘土板、陶器、土器、そして銅、象牙が少々。
文字は「概念」だけが伝わり、「実体」は各文明で実装されたのだろう。
文字の媒体で、面白いのはパピルスだ。
たかがパピルス、されどパピルス、紀元前250年頃おこった図書館戦争の主役になったのである。
古代最大の図書館とえいば、エジプトのアレクサンドリア図書館だ。当時エジプトを支配していたのはプトレマイオス朝。その歴代の王たちは、地中海世界中の書を集め、パピルスの写本を制作した。それを図書館に収蔵し、アレクサンドリアを世界の「知の中心」にしようともくろんだのである。蔵書数は、パピルスの巻物で数十万~100万巻で、古代世界最大。現代の中規模図書館に匹敵する。
これに対抗心を燃やしたのが、小アジアのペルガモン王国だ。王都ペルガモンに大図書館を建設し、アレクサンドリア図書館に対抗したのである。エジプトから輸入したパピルスで写本を制作し、ペルガモン図書館の蔵書数は急増した。焦ったプトレマイオス朝は嫌がらをせする。パピルスの輸出を禁止したのである。
当時、パピルスはエジプトの特産品で、他では入手できなかった。パピルスの原料となるカミガヤツリ(パピルス草)は、エジプトにしか産しなかったからだ。それでも、ペルガモン王国はあきらめない。パピルスのかわりに、羊、子牛、ヤギの皮で作った羊皮紙を発明したのである。つまり、羊皮紙の「発明の母」は、エジプト王国とペルガモン王国の図書館戦争だったのである。
羊皮紙は丈夫だが、高価だ。一方、パピルスは安価だが、湿気がある地域では長持ちしない。そのため、紙が発明されるまでは、乾燥した地中海世界はパピルス、湿気の多いヨーロッパ内陸部では羊皮紙が使われた。
ちなみに、パピルス「papyrus」は紙「paper」の語源になっている。
ここで、コーヒーブレイク、私的パピルス・トピックスを紹介する。
25年前のことだ。
東京駅前に日本有数の大書店「八重洲ブックセンター」があった。東京出張の帰りによく寄ったのだが、あるとき、一階の片隅で「パピルス」を売っていた。書店の正規の売り場ではなく、間借りした臨時販売店だ。
マニアックな風貌のおじさんが「これはエジプトで売っているお土産物とは別物です。ウチが工程を指示して作らせた正真正銘のパピルスです」と力説していた。宙の一点を凝視したまま、熱く語る姿に圧倒され、数枚購入した。
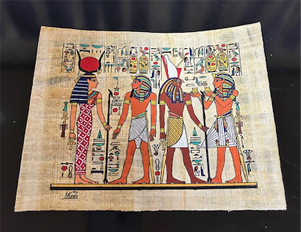
写真は、そのときのパピルスだ。表面がザラザラしていて、センベイみたいで、曲げるとパリッと破れそう。ビビッドではないが、鮮明で上品な着色である。左側に立っているのは豊穣・再生の女神・ハトホルだが、それは重要ではない。肝心なのは、これが本物の古代パピルスです!
その後、このパピルスおじさんは、みかけなくなった。さらに、2023年3月、八重洲ブックセンターそのものが閉店してしまう。今となっては、懐かしい思い出だ。
■頂点捕食者はダモクレスの剣
話をもどそう。
4万年前、ネアンデルタール人は、ホモ・サピエンスによって滅ぼされた。
能力に大差はなく、交配までしていたのに、なぜか?
確たる証拠はないが、モノゴトを抽象化する能力ではないか。
ホモ・サピエンスは、35万年で文字を発明したが、ネアンデルタール人は36万年たっても発明できなかった。文字は、抽象的思考がかかせない。そして、抽象的思考は、高度な文明・文化を生む原動力である。
地球の食物連鎖は、ビミョーな差で成り立っている。その小さな差が、巨大な差となり、頂点捕食者を決定するのだ。
1億年前、食物連鎖の頂点に立ったのは巨大な恐竜だった。図体がデカいほど、ケンカに強いから当然だろう。
ところが、6600万年前、巨大隕石が地球に衝突した。
地球上の植物と動物が激減し、大飯喰らいの恐竜は絶滅する。すると、地中で縮こまっていた小さな哺乳類が地上に顔を出した。恐ろしい捕食者(恐竜)がいなくなったからだ。
哺乳類は、恐竜とは異なる方向に進化した。腕力を捨てて、知力に賭けたのである。
結果、賢い種族があらわれた。ヒト属である。
ヒト属は、190万年前のホモ・ルドルフエンシスから始まった。40万年前にネアンデルタール人、少し遅れて、ホモ・サピエンスが出現。ホモ・サピエンスはネアンデルタール人を駆逐し、文字を発明し、科学を飛躍的に発展させた。蒸気機関、電動モーターと人工動力を獲得し、原子力の灯をともし、人間を月におくりこんだ。最近は、AI開発に夢中だ。
現在のAI「大規模言語モデル(LLM)」が、一皮、二皮むければ、AGI(人工汎用知能)に進化するだろう。つぎに、AGIが再帰的自己改善をくりかえせば、間をおかず、ASI(人工超知能)に達する。その瞬間、ホモ・サピエンスは食物連鎖の頂点から転落する。代わりに、玉座に座るのはASIだ。
これが、これから起こる地球の進化である。
ホモ・サピエンスは自然の産物、AGIはホモ・サピエンスの産物、すべて自然がからんでいる。ところが、ASIは違う。機械による、機械のための、機械なのだ。しかも、有機生物の何億倍ものスピードで進化する。怪物どころではない。機械仕掛けの神なのだ。
頂点捕食者の玉座はかくも危うい。
さながらダモクレスの剣ではないか。
参考文献:
・年表で見る科学の歴史図鑑 DK社 (編集), 井山 弘幸 (監修), 伊藤 伸子 (翻訳) 出版社:化学同人
by R.B