鉄の歴史(2)~鉄の文明と未来~
■鉄の技術は東高西低
子供の頃、科学技術では日本は欧米にはかなわないと教えられた。歴史年表をみれば明らかで、言うまでもない。16世紀、ヨーロッパ人たちは遠くアメリカ大陸やアジアまでやって来て、町や村を荒らし回り、植民地にした。原因は白人だけがもつ「命知らずの冒険遺伝子」にあるが、大砲とガレオン船もこれに劣らず重要である。ここで、「命知らずの冒険遺伝子」はものの喩えではなく、実在する遺伝子である。
当時、アジアの貧弱な船では、太平洋や大西洋を航海するのはムリだった。その頃、インド商人やイスラム商人はヨーロッパとアジアを結ぶ交易を行ったが、陸地を見ながら陸沿いに航海したのである。太平洋のど真ん中を突っ切ったわけではない。そんな大技ができるのはヨーロッパのガレオン船ぐらいだった。
また、ヨーロッパ人が大砲をぶっ放せば、アジア人は蜘蛛の子を散らすように逃げ去った。少なくとも、近代から現代の歴史では、科学技術は西高東低であった。
ところが・・・
鉄の歴史となると東高西低、立場は逆転する。歴史上、初めて鉄の製錬に成功したのはオリエント(ヒッタイトかアッシリア)。歴史上最高品質の鋼鉄を製造したのはインドであった。1976年アメリカで、「ウルトラ・ハイ・カーボン・スチール」という超高硬度の炭素鋼が発明されたが、それは1000年前のインドの「ウーツ鋼」そのものだった。つまり、製鉄の歴史では、オリエント(東方)が西方を圧倒したのである。
ところが、この優位はやがて逆転される。ヨーロッパのいたるところで、オリエントの製鉄技術がコピーされたからである。今、アジア諸国はオリジナリティがなく、欧米を真似てコピーするだけ、と揶揄されているが、地球全時代を通じて真実というわけではない。
■ヨーロッパの製鉄
鉄を得る方法は大きく2つある。地球に衝突した隕鉄をそのまま使う方法、鉄鉱石を製錬する方法である。現在、製鉄といえば後者をさす。一般に、鉱石から金属を抽出することを「製錬」と言い、それが鉄なら「製鉄」。
16世紀のヨーロッパではすでに製鉄が行われていたが、その工程は次のようなものだった。まず、高炉の中に、鉄鉱石と木炭をいれ、加熱する。なぜ木炭を入れるかというと、鉄鉱石の酸化鉄から酸素をうばい、鉄を抽出するためである。「木炭=炭素」なので、酸素と結合しやすいのである。化学式であらわすと、
「C+O2=CO2」
結果、酸化鉄(Fe2O3)から酸素(O)が引き離され、鉄(Fe)だけが残る。
「Fe2O3+3CO=3CO2+2Fe」
一方、鉄鉱石を融かすには高温が必要だ。相手は鉱石、薪をくべて、燃やしてみたところで、どうにもならない。そこで、大量の酸素を強制的に送り込み、燃焼を加速させるのである。送風には、ふいごが使われたが、人力ではやはり限界があった。16世紀に入ると、自然の力を利用した水車が使われるようになる。水車は、風まかせの風車にくらべ、ずっと安定していたからである。
これは木炭高炉法と呼ばれ、銑鉄(せんてつ)と錬鉄(れんてつ)を抽出できる本格的な製鉄法だった。ここで、銑鉄とは炭素を多く含む鉄で、錬鉄は逆に炭素の含有量が少ない。その中間が「鋼鉄(はがね)」である。
こうして、ヨーロッパでは、機械化により、鉄の量産が可能になったが、一方で、設備投資額も増え続けた。ところが、時期を同じくして、新しい経済システムが生まれようとしていた。資本主義である。おカネの使い道に困った金融資本家たちがこぞって、製鉄業に投資したのである。南ドイツの豪商フッガー家もその1つだった。この名家は、1517年の宗教改革で、免罪符を売りさばいて悪名をとどろかせたが、製鉄でも巨万の富を得たのである。
ところが、順風満帆にみえた製鉄業に意外な落とし穴があった。木炭高炉法は大量の木炭を消費するが、その結果、森林資源が枯渇したのである。とくに、イギリスは深刻だった。森林資源が少ないのに、製鉄業が盛んだったからである。ロビン・フッドが活躍したシャーウッドの森もいつの間にか消えていった。
一方、この事態を大喜びする国もあった。森林資源が豊富なスウェーデンとロシアである。そのまま推移していれば、産業革命はスウェーデンやロシアで起こっていたかもしれない。製鉄業と蒸気機関は一心同体だからである。そうなれば、歴史は大きく変わっていただろう。しかし、歴史はイギリスに味方した。
■第4作「コークス炉」
イギリスの歴史を見ると、国民性として、負けず嫌い、勤勉、冒険心がある。冒険心は、冒頭の「命知らずの冒険遺伝子」と関係がある。というわけで、イギリスは製鉄業で他国に遅れをとるのは我慢ならなかった。鉄鉱石(酸化鉄)から酸素を抜き取るのは炭素だが、なにも木炭だけが炭素ではない。石炭も立派な炭素である。そして、イギリスは世界有数の石炭産出国だった。イギリスは、さっそく石炭に飛びついたが、やっかいな問題があった。石炭に含まれる硫黄(イオウ)が、鉄をもろくするのである。
それでも、イギリス人はあきらめなかった。今度は、石炭ではなくコークスに目をつけたのである。コークスは、石炭を蒸し焼きしたものだが、同時に、硫黄など不純物も燃え尽きる。まさに、一石二鳥。イギリスはコークス製錬で国難を乗り越えたのである。
もし、コークス高炉がなければ、製鉄業で、イギリスはスウェーデンやロシアの後塵を拝していただろう。それだけではない。製鉄業で遅れをとれば、それに続く、産業革命、機械革命、電気革命でも遅れをとる。コークス高炉は歴史を変える大発明だったのだ。こうして、コークス高炉はイギリスに300年の繁栄をもたらした。
一方、スウェーデンやロシアが製鉄業を制する歴史では、産業革命はかなり遅れた可能性がある。産業革命は、イギリスの政治制度、経済制度、地理的条件、そして国民性に大きく依存しているからだ。もし、コークス高炉が発明されなかったら、今も、家の灯りは白熱電灯だったかもしれない。
というわけで、ブータン鋼鉄切手の第4作目は「コークス高炉」。この選択には、ブータン政府の鉄に対する深い理解が感じられる。また、第4作目のプリントは、8部作の中で唯一、淡い色調の図柄となっている。リアルではなく、シャレたイラスト調。
■蒸気機関
イギリスは、コークス高炉の発明で、製鉄業の頂点に立った。イギリス人は石炭を掘りまくり、それをコークスに変え、鉄の量産に励んだ。ところが、またもや問題発生。石炭を地下深く掘るほど、大量の水が湧き出たのである。湧き水といっても、はんぱな量ではない。採掘の妨げとなり、時には、炭坑労働者の命を奪った。
とにかく、湧き出た水を排出するしかない。排水には、人手や風車による揚水ポンプが使われたが、効率が悪かった。このような「必要」から生まれたのが蒸気機関だった。まさに、必要は発明の母。先の「製鉄業で遅れをとれば、産業革命も遅れをとる」の根拠はここにある。歴史とは因果の連鎖、孤立しているもの、偶然の産物などないのだ。
1712年、イギリスのニューコメンは、歴史上初めて蒸気機関の実用化に成功した。この蒸気機関は、蒸気を冷やすと水に戻り、圧力が下がるが、その吸引力を利用するのである。出力は8馬力程度で、後のワットの蒸気機関よりずっと効率が悪かった。それでも、深さ80mの水を汲み上げることができた。このニューコメンの蒸気機関のおかげで、以前の2倍の深さまで採掘が可能になったのである。
そして、1769年、ワットが新しい蒸気機関を発明する。スコットランド生まれのジョームズ・ワットは、子供の頃から天賦の才をあらわした。ワットは有能な機械職人だったが、数学のセンスも抜群だった。理論面では大学教授がサポートし、技術面では様々の分野の技術者たちが彼を助けた。ワットを取り巻く環境は、蒸気機関を発明するにはうってつけだったのである。
ワットの蒸気機関の最大の功労者は、おそらく、イギリスのJ・ウィルキンソン。もし、ウィルキンソンが発明した「中ぐり盤」がなければ、ワットの蒸気機関は歴史上、「すばらしい思いつき」で終わっていただろう。
蒸気機関は巨大な機械装置である。長さ3mを超える長大なシリンダー中を、ピストンが往復運動する。シリンダーとピストンのすき間が大きいと、水蒸気がもれて効率が悪い。高い精度で、シリンダーをくり抜く必要があった。実際、ワットはこのシリンダーの製造に手を焼いていた。
ところが、ウィルキンソンの中ぐり盤は、どんな寸法でも、中をくり抜くことができた。しかも、シリンダーとピストンのすき間はわずか1.5ミリ。ウィルキンソンの中ぐり盤は「くり抜き作業」の銀の弾丸だったのだ。
一方、手の器用なウィルキンソンは、ワットの蒸気機関を勝手に組み立てて、自分の工場で使用した。特許料も払わずに。だが、ウィルキンソンなくして、ワットの蒸気機関はありえない。この程度の盗用は目をつむってもいいだろう。ということで、ワットの歴史的名声はウィルキンソンのおかげ?
■鉄道
歴史の因果はさらにつづく。石炭採掘の揚水の問題は、蒸気機関がクリアした。つぎは、石炭の大量輸送である。当時のイギリスは、石炭輸送はトロッコと木製レール(陸上輸送)と、運河(水上輸送)に頼っていた。トロッコは運べる量は少ないし、木製レールはすぐに壊れる。一方、運河は運べる地域が限られた。
このような大量輸送の問題を、一気に解決するのが鉄道だった。鉄道があれば、石炭を大量にどこにでも運べる。つまり、
「製鉄→石炭の大量輸送→鉄道(蒸気機関)」
ところが、歴史の因果はさらにつづく。鉄道が生まれるまでは、都市の周辺に農産物を生産する農村が必要だった。都市と農村が離れていると、野菜などの生鮮品が都市に届くまでに腐るからである。ところが、鉄道があれば、野菜をその日のうちに運ぶことができる。こうして、都市と農村の機能が完全に分離された。新しい分業社会が誕生したのである。つまり、
「鉄道(蒸気機関)→都市と農村の機能分離→新しい分業社会」
こんな風に歴史を俯瞰すると、機械文明の起源は「製鉄」に見えてくる。
1810年、フランスでも本格的な製鉄業が始まった。プジョー兄弟が、水車を利用して、金属加工業を始めたのである。その後、プジョー兄弟は蒸気機関を利用し、製品のバリエーションを増やしていった。斧、のこぎり、かみそりの刃、コーヒーミル、そして自動車へと。これが世界有数の自動車メーカー、プジョーの起源である。洗練されたルックス、他社が真似るビビッドで上品なカラー。「ネコ足プジョー」と称賛されるしなやかな足回り。自動車の名門プジョーも、200年前は鍛冶屋だったのである。
■鉄の限界
技術の歴史にゴールはない。コークス高炉により、鉄の量産が可能になったが、今度は、鉄道が新たな問題を生んでいた。当時、鉄道のレールは錬鉄でつくられていた。錬鉄は炭素成分が少なく、軟らかく加工しやすかったからである。反面、摩耗するのがはやく、変形しやすかった。レールが簡単に摩耗、変形してはたまらない。イコール、脱線転覆なので。
錬鉄がダメなら、銑鉄を使う手もあった。銑鉄は炭素を多く含むため、硬くて摩耗が少ないからである。ところが、もろすぎて、使い物にならなかった。レールが割れたら、やっぱり、脱線転覆。
では、軟らか過ぎず、もろ過ぎず、硬くて丈夫な鉄はないのか?ある。それが鋼鉄だ。鋼鉄は、炭素の含有量が錬鉄と銑鉄の間にあり、硬くて、粘りがあって丈夫。ただし、問題があった。安価に大量生産できないのである。当時の製鋼法のスタンダードは「るつぼ製鋼法」。1740年頃、イギリスのベンジャミン・ハンツマンによって発明された。
るつぼ製鋼法は、耐火性のるつぼに、錬鉄と木炭を封印し、炉に入れ、コークス等の燃料を燃やして加熱する。すると、錬鉄に炭素が浸透して鋼ができあがる。品質は最高だったが、大量の燃料を消費し、生産コストも高い。しかも、1回で生産できる量は30~40kg。刃物やぜんまいに使うのがせいぜいだった。ましてや、長大な鉄道レールに使うことなど論外。
■第5作「ベッセマーの転炉」
1856年、製鉄業で歴史的な革命が起こった。イギリスのベッセマーが「ベッセマー転炉」を発明したのである。ベッセマー転炉は、短時間で、安価に、大量に、鋼鉄を生産できた。しかも、桁違いに。るつぼ製鋼法では1回の生産量は30kgだったが、ベッセマー転炉は25トン!ざっと1000倍である。しかも、所要時間はたった30分で、燃料は不要。まるで魔法である。
ここで、ベッセマー転炉の魔法のからくりを見てみよう。じつは、ベッセマー転炉はるつぼ製鋼法と真逆の方法をとっている。るつぼ製鋼法は、炭素の少ない錬鉄に炭素を加えるのだが、ベッセマー転炉は炭素の多い銑鉄から炭素を抜き取るのである。
その原理は驚くほど簡単だ。高炉で融かした銑鉄を転炉に入れ、底から空気を吹き込む。すると、銑鉄の中の炭素は、吹き込んだ空気中の酸素と化合し、一酸化炭素として抜けていく。炭素成分が1.7%を切ったところで、吹き込むのを止めれば完了。炭素含有量が1.7%の鋼鉄のできあがり。ここで、燃焼させる燃料として、銑鉄の炭素を利用しているのがミソだ。つまり、燃料は不要。おまけに、人手もほとんどかからない。結果、鋼鉄の価格は数分の一まで下落した。シンプルイズベスト、これこそ「オッカムのカミソリ」。
 こうして、鋼鉄は、鉄道、土木建築、船、車、日用品と、あらゆる分野で使われるようになった。本格的な鉄の文明が始まったのである。ブータン鋼鉄切手の第5作目にベッセマー転炉が選ばれたのは必然である。鋼鉄の大量生産なくして、現代文明はありえない。しかも、その最大の功労者がベッセマー転炉なのである。(写真は鋼鉄切手の第5作「ベッセマー転炉」)
こうして、鋼鉄は、鉄道、土木建築、船、車、日用品と、あらゆる分野で使われるようになった。本格的な鉄の文明が始まったのである。ブータン鋼鉄切手の第5作目にベッセマー転炉が選ばれたのは必然である。鋼鉄の大量生産なくして、現代文明はありえない。しかも、その最大の功労者がベッセマー転炉なのである。(写真は鋼鉄切手の第5作「ベッセマー転炉」)
ところで、日本の製鉄業は?1857年、釜石市で近代的な大橋高炉が建造されている。だから、日本もそれほど遅れていたわけではない。
■第8作「未来の鋼鉄文明」
ブータン鋼鉄切手の最後は「未来の鉄文明」。タイトル通り、鉄の未来が描かれている。この未来世界では、超高層ビルが建ち並び、立体道路がその間をぬい、異形の車が走行している。40年前、雑誌を飾った未来図は、だいたいこんなものだった。
だが、ブータン鋼鉄切手の未来図には、ユニークが点がある。都市全体が透明っぽいのだ。これはある重大な発明を示唆している。「未来の鉄文明」がテーマなら、都市全体が鉄でできているはず。それが透明っぽいということは、「透明の鉄」が発明された!?考えただけでワクワクする。図柄はアメコミ調で、このテーマにピッタリ。
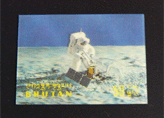 ブータンは他にもユニークな切手を発行している。この写真の切手は、じつは、立体写真切手。歴史上初の月着陸を記念したものである。アポロ宇宙船、月着陸船、月面の宇宙飛行士と、こちらも複数の種類がある。ブータンは農業国だが、技術者のオタク心をくすぐる術を心得ている。なんとも、心惹かれる国である。
ブータンは他にもユニークな切手を発行している。この写真の切手は、じつは、立体写真切手。歴史上初の月着陸を記念したものである。アポロ宇宙船、月着陸船、月面の宇宙飛行士と、こちらも複数の種類がある。ブータンは農業国だが、技術者のオタク心をくすぐる術を心得ている。なんとも、心惹かれる国である。
《完》
参考文献:
金光不二夫他訳ソ連科学アカデミー編「世界技術史」大月書店
by R.B


