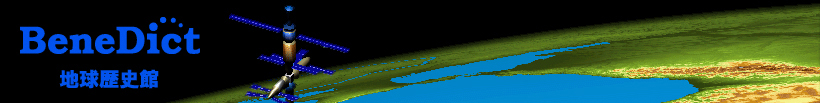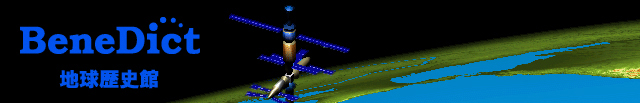神の計画とメタ認知~超越する意識~
■全能の神
神はいるかもしれないが、人間には無関心だ。
意外かもしれないが、神は全能ではない。
やることなすこと行きあたりばったりなので。
たとえば「生物の進化」。
生物の設計図「遺伝子」から個体が造られ、弱肉強食の過酷な戦場「自然選択」に送りこまれ、淘汰される。生き延びた個体の遺伝子だけが子孫に継承され、種は存続する。一方、個体数がゼロになった遺伝子は、継承できなくなり、種は絶滅する。4万年前に滅んだネアンデルタール人のように。
進化の原動力は「自然選択(自然淘汰)」である。
ただし、「選択」には、全知全能を思わせるような神々しい仕掛けはない。過去の記憶も、未来への展望も、洗練された計画もない。何千万年、何億年もかけた泥臭い試行錯誤の繰り返しだ。
つまり、進化とは、トップダウンではなく、ボトムアップの漸進的改良なのである。
これが全知全能の御業?
いえいえ、神はそんなドタバタ劇をみて楽しんでいるのです。
だとしたら、ドタバタをやらされる方はたまらない。繁栄を極めた恐竜さえ、隕石衝突の一撃で絶滅するのだから。
ルイス・キャロルの「鏡の国のアリス」の中で、赤の女王はアリスにこう言う。
「この国では、同じ場所にとどまるためには、全力で走り続ければなりません」(※1)
素晴らしいブックデザイナーで、作家でもあるユーディット・シャランスキーは、名著「キリンの首」の中でこう言っている。
「生物間を支配するのは、競争の原理です。ワシやライオンを捕食する動物は存在しません。それが事実です」(※2)
なんとも世知辛い世界ではないか。
■人間と動物とAIの認知
さて、生物が「自然選択」を乗り切るためのツールが「知能」だ。
外界の状況を把握し、適応する能力で、外界とのコミュニケーション能力とも言える。
知能は、生存にかかわる複雑な能力なので、頭の良し悪しのような単純な物差しでは測れない。
もし、知能が学力やIQで決まるなら、自然選択で生き残るのは人間しかいない。さらに、人間社会でも、偏差値高い系しか勝ち残れない。ところが、実際は、地球上の動物だけで約650万種いるし、人間社会における成功も、学力やIQに直結しない。ノーベル賞の受賞者でさえ、IQの中央値は110程度なのだ。
知能は、頭の良さより、賢さ?
相関関係は成立している。
そもそも、頭の良さは、読み書きソロバンにすぎない。一方、賢さは、進化の大原理「自然選択」に直結している。
これには事情がある。
賢さは、現実世界をシミュレーションする能力なのだ。
というのも、現実世界はあまりに複雑すぎて、そのままでは脳は理解できない。
マクロ世界はニュートン力学で、ミクロ世界は悪魔の理論「量子力学」で、さらに、状況や場合によって、熱力学やら生物学・・・ところが、これらの仰々しい理論も、仮説の域を出ない。真実である保証は1ミリもないのだ。
そんなわけで、人間でさえ、ほとんどの処理を、反射的にやっている。お腹がすいたら、ニュートン力学、量子力学、生物学で分析して解決する人はいないだろう。食べ物を見つけて、さっさと胃袋に放り込むだけ。
まさに「認知のショートカット」だが、カラクリはこうだ。
複雑な現実世界を、脳が理解できるように簡略化した世界モデルを構築する。それでシミュレーションすれば、脳内部で現実世界が再現できるわけだ。たとえば、我々は現実世界を3次元でとらえているが、そんな単純なものではないだろう。リンゴは丸みを帯びた赤い球体にみえるが、実体は、無数の原子でできている。もちろん、リンゴを原子レベルで観察している人はいない(たぶん)。
さらに、世界モデルは種によって異なる。
人間の世界モデルは、ほどほどの視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚を前提にしている。ネコの世界モデルは、人間を凌駕する動体視力と聴力を前提に構築されている。一方、コウモリの世界モデルは、視覚にくわえ、超音波を利用する。入力データのフォーマットが違うのだから、世界モデルも違って当然だ。
では、機械知能のAIは?
現在主流の大規模言語モデル(LLM)は、テキスト頼みだが、2025年、エヌビディアのジェンスン・ファンCEOは「世界モデル」の構想をぶちあげた。AI内部に、現実世界を模した世界モデルを構築し、外界の情報をIoTを介して取り込み、シミュレーションして、現実世界を再現する。現実世界をコンピュータ内部にコピーするデジタルツインもその一つだ。
今後、AIは「生成AI → AIエージェント → フィジカルAI(物理AI)→ AGI(人工汎用知能)→ ASI(人工超知能)」と進むのは明らかだ。
お気づきだろうか?
AIがどこへ進もうが、GPUは欠かせない、よってエヌビディアだけが丸儲け。エヌビディアは時価総額世界一だが、売上でもウォルマートを抜いて世界一になるのは時間の問題だ。
話をもどそう。
ジェンスン・ファンの世界モデルは、人間や動物や生成AIが、現実にやっていること。つまり、人間も動物もAIも「認知」のカラクリは同じなのだ。
一方、「認知」には段階がある。
■認知症と見当識
長生きすると、良いことばかりではない。
男女、富貴を問わず、認知症のリスクが急増するからだ。
じつは、認知症は「見当識」で容易に判定できる。
「見当識」とは、自分がおかれている状況を、時間的、空間的、社会的に正しく認識できる機能。認知症が進むと、見当識の障害が段階的にあらわれる。
まず、今日は何日?(時間的)、つぎに、ここはどこ?(空間的)、さらに、あなた誰?(社会的)、最後に、私は誰?
つまり、見当識(認知機能)は難しい順番に、時間、空間、社会なのだろう。
では、動物に見当識はあるのか?
たとえば、ネコ。
なぜ、トートツにネコかというと、この小動物が、他の動物をさしおいて、地球を征服しつつあるからだ。
昔、「インベーダー」という米国SFドラマがあった。
タイトルそのままで、地球征服もくろむ異星人の話だ。若き建築家デビッド・ビンセントは、帰宅途中に、偶然、宇宙からの侵略者を目撃する。ビンセントは、地球がインベーダー(侵略者)によって侵略されつつあると訴えるが、誰も信じてくれない。それもそのはず、インベーダーは人間にそっくりなのだ。人間と違うのは、小指がうまく曲がらないこと。このドラマのせいで、人と出会うたびに、小指をチェックするクセがついてしまった(今は完治している)。
一方、ネコの地球征服はドラマではない。現実の問題なのだ。
根拠がある。
イエネコの総数は、世界で6億を超え、一大勢力にのしあがっている。ペットの地位を二分していたイヌを抜き去り、3倍に達している。しかも、その差は広がるばかり。ここで、イエネコとは、野生のネコではなく、人間社会に暮らすネコをさす(野良ネコを含む)。
これはおかしい。
ネコは、ライオン、トラ、ヒョウ、チーター、サーベルタイガーと同じ哺乳綱食肉目ネコ科に属するが、増えているのはネコだけ。
かつて、ライオンは百獣の王といわれたが、今は見る影もない。アフリカのいくつかの自然保護区とインドのたった一つの森に、2万頭が生き残っているだけ。しかも、現在も減り続け、生物学者たちによれば、今世紀末には絶滅する可能性があるという(※3)。
ちなみに、長さ20センチの恐ろしい犬歯をもつサーベルタイガーは、1万年前に絶滅している。
最強のライオンが、自然選択の負け組で、小柄で生意気なネコが勝ち組?
やっぱりおかしい。
けれど、不自然なものには必ず理由がある。
まず思いつくのは、ネコが人間社会の家族の一員になっていること。最強の頂点捕食者の庇護下にあるのだから、当然だろう。
とはいえ、地球上に動物は650万種もいるが、これほど人間社会に入り込んでいるのは、イヌとネコぐらい。そのイヌもネコの1/3にすぎないのだ。
ネコは見た目が愛くるしいが、それだけではないだろう。読み書きソロバンはできないし、しゃべれないし、愛想もないが、人間の「認知」に共鳴する何かがあるのだ。
■スナネコの認知能力
スナネコが毒蛇を捕食する映像をみた。
毒蛇は、頭を持ち上げ、噛みつこうとするが、スナネコは軽くかわし、毒蛇の頭が伸び切ったところで、必殺のネコパンチ。蛇の反応速度は0.04秒と動物界でトップクラスだが、ネコの反応速度は0.02秒で、2倍も敏速だ。その差は歴然で、10回ほどの攻防で毒蛇は絶命した。ところが、スナネコは、毒蛇の横に座りこみ、すぐに食べない。
なぜか?
ここでスナネコの認知を分析しよう。
スナネコは、すぐに食べたいのはやまやまだが、激しい戦いで体力を消耗している。死んだ蛇は逃げないからあわてて食べる必要はない。餌を横取りする不埒な輩がいるかもしれないが、警戒すれば対応できる。
そこで、獲物の横に座り込み、息を整えながら、周囲を観察しつつ、回復を待って、食事にありついたのである。
お気づきだろうか。
スナネコは、自分が置かれている状況を、時間的、空間的、社会的に総合的に理解し、判断している。つまり、見当識を獲得しているのだ。
ネコは、イヌのように新聞をとって来てくれないし、尻尾を振って愛想をふりまくこともない。昔は、ネズミ捕りで貢献したものだが、今はネズミと遊んでいる。そんなこんなで、イヌはネコが役立たずだと見抜いているが、人間はそれに気づかない。結果、いつのまにか、ネコは人間社会を侵略し、一大勢力を築いたのだ。
ネコが、見当識をもっていても、不思議ではない。
■メタ認知と哲学
認知には、時間、空間、社会の3つの段階があるが、その上位にあるのが「メタ認知」だ。
「メタ」は「より高次の」を意味する。
よって「メタ認知」は、超認知のことで、思考や感情などの日常の認知を、上から目線でモニターし、コントロールする。脳が2つあって、一つは日常の知的活動、もう一つは、それを監視しているイメージだ。
たとえば、毎日のように、書店に通う人。
自分は、無類の読書家、インテリと思いこんでいるが、事実は違う。本当の読書好きなら、図書館に行けばいいわけで、わざわざ書店へ行って、身銭を切って本を買う必要はないだろう。
じつは、読書家ではなく、本の収集家なのだ。
証拠がある。
この手の似非インテリは、膨大な本を買い集めるが、数ページ読んだだけで、本を積み上げていく。これを「積読(つんどく)」という。自分がやってることなので、間違いないです。
さて、ここでメタ認知の登場。
本に執着する知的活動が認知、それを上から目線で俯瞰し、読書家か収集家を判定するのがメタ認知なのである。
ただし、メタ認知にも段階がある。
自分をとりまく環境を把握し、生き延びるため、あーでもない、こーでもないと考える。これが認知だ。さらに、考えること自体間違っていないか、意識するのがメタ認知である。つまり、この最上位のメタ認知は、認知の内容ではなく、認知すること自体を疑っているわけだ。
それって、哲学?
イエス、メタ認知と哲学には深い関係がある。
というのも、メタ認知が「高次の認知」なら、その判断基準が「哲学」だからだ。
哲学を参照しながら、今考えていることは、かくかくしかじかで、間違っている、いや大丈夫、とジャッジするわけだ。
つまり、哲学は「認知の地図」で、メタ認知はその地図を見ながら、人生を旅することなのである。
じゃあ、メタ認知と哲学があれば、人生は安泰、人間は幸福になれる!?
残念ながら、そうでもなさそうだ。
2024年の日本の自殺者は2万320人だという。
参考文献:
(※1)詳注アリス 完全決定版 マーティン・ガードナー (著), ルイス・キャロル (著) 出版社:亜紀書房
(※2)キリンの首 ユーディット・シャランスキー (著), 細井 直子 (翻訳) 出版社:河出書房新社
(※3)猫はこうして地球を征服した: 人の脳からインターネット、生態系まで アビゲイル・タッカー (著), 西田美緒子 (翻訳)出版社:インターシフト
by R.B