格差社会の行き着く先~問題点と解決策~
■広がる格差
地球上の「富める者」と「貧しき者」を黄金の天秤(てんびん)にかけると・・・
富裕層上位80人の資産総額=貧困層35億人の資産総額
富裕層上位1%の資産総額=残る99%の資産総額
ありえない・・・
ところが、これで驚いてはいけない。貧富の差はさらに拡大しているのだ。
たとえば、米国では・・・
時給10ドル前後の低賃金労働は、リーマンショック時には全体の20%だったが、その後、60%に拡大している。
一方、日本でも・・・
「相対貧困率」は増加の一途をたどっている。「相対貧困率」とは、全世帯の中央値(年収244万円)の半分に満たない貧困者の比率で、2010年で16%。つまり、全世帯の16%が年収122万円以下で暮らしているわけだ。
さらに・・・
OECDの2010年の統計によれば、日本の相対的貧困率は世界で第6位(調査した国の中で)。弱肉強食を極めたアメリカ合衆国の「17.4%」に次ぐ高さなのだ。しかも、国家破綻がウワサされたギリシャの「14.3%」より高い。
一体どうなっているのだ?
日本は、貧富の差が世界一小さい国だったのでは?
たしかに、今の世相をみると、貧困女子、若者の貧困・・・若年層の貧困の問題が目立つ。とくに、20代の若者で、働いても生活が成り立たない貧困を「ワーキングプア」とよんでいる。このような若年貧困層が30~40%も占めるという。「下流老人」、「中年ニート」も問題だが、人生これからの若者世代がこれでは夢も希望もない。
日本はいつからこんな国に成り下がったのか?
格差の問題は2つある。
格差の「大きさ」と「増加率」だ。両方とも大きいのだから、格差は広がるばかり、行き着くところは「ディストピア」しかない・・・
ディストピア?
ユートピア「理想郷」の真逆、究極の格差社会「暗黒郷」だ。古典映画の名作「メトロポリス」を彷彿させるではないか。
■究極の格差社会
「メトロポリス」はSF映画の原点と目されているが、じつのところ、究極の「ディストピア」映画なのだ。1926年、ドイツのフリッツ・ラング監督によって製作されたが、今ではお目にかかれない白黒・無声映画。ところが、インパクトは超弩級、90年前の映画とは思えない。
ストーリーは一大叙事詩の風格がある・・・
2026年、壮大で威厳にみちた巨大な摩天楼がそびえ立つメトロポリス。その摩天楼の上層階に優雅に暮らす支配階級、一方、地下で過酷な労働を強いられる労働者階級・・・この世界は完全に二極化された階級社会なのだ。
ところが、どんな世界にも醜いアヒルの子はいる。支配階級のリーダー・フレーダーセンの息子フレーダーもその一人だった。彼は労働者階級の娘マリアに一目惚れし、地下社会に同情するようになる。一方、マリアもフレーダーを支配階級と労働者階級の橋渡しとして期待する。
それを知ったフレーダーセンは悪魔のような計画を思いつく。科学者のロトワングにマリアに似せたアンドロイドを作らせ、本物のマリアとすり替えたのである。アンドロイド・マリアを地下社会へ送り込み、労働者の団結を破壊するために。
ところが、科学者ロトワングはフレーダーセンに深い恨みを持っていた。そこで、この計画を利用して、メトロポリスを破壊しようとしたのである。ロトワングの密命をうけたアンドロイド・マリアは、地下社会の男たちを虜(とりこ)にし、扇動してメトロポリスの心臓部を破壊してしまう。
一方、労働者たちはアンドロイド・マリアに扇動されていたことに気づく。怒り狂った労働者たちはマリアを火あぶりの刑にしたが・・・炎の中から現れたのは機械仕掛けのマシンだった(アンドロイド・マリアは映画史上最も美しいアンドロイドといわれている)。
その後、助け出された本物のマリアとフレーダーは支配階級と労働者階級の和解の道を模索する。
ということで・・・
映画「メトロポリス」の格差社会はアンドロイド・マリアによって破壊された。一方、現実世界のヨーロッパの格差社会は、フランス革命によって粉砕された。
では、今の格差は誰が解決するのか?
じつは、格差を是正する仕掛けはすでにある。たとえば、累進課税。所得が多いほど、税率を指数関数的に高くして、富める者からたくさん税金をとる。それを、国のインフラやサービスにまわせば、富の再分配が行われる。結果、貧富の差が収束するというわけだ。
ではなぜ、現実はそうなっていないのか?
累進課税は給与所得が対象で、株の配当や売買益には適用されないから。
たとえば、年収が1億円とすると・・・給与で稼いだら税率は50%、株の配当や売買益なら税率20%。
もちろん、後者の恩恵にあずかれるのはお金持ちだけ。食うや食わずの人が株など買うわけないから。
だから、金持ちほどお金は増える、格差が広がるのはあたりまえなのだ。
じつは、ココに目をつけたのが、経済学者トマ・ピケティだった。
■ピケティの21世紀の資本
ピケティが著した「21世紀の資本」は世界中でベストセラーになった。2014年、日本語版も出版されたが、やはりベストセラーに。こんな小難しい、しかも、700ページをこえる経済書が、なぜ売れたのか?
現代の深刻な問題「格差社会」を扱ったから。しかも、推測や憶測ではなく、膨大な資料をベースにしている。
ピケティは、過去300年間の各国の税務資料を調査し、貧富の差は、戦後の一時期をのぞいて、増え続けていることを発見した。そして、その原因をカンタンな式で表したのである。
資産の増加率>給与所得の増加率
一言でいうと、給料が増えるより、資産が増える方が速い!
たとえば・・・
資産運用で代表的な投資信託や株式の年間リターンは平均3~40%ぐらい。もちろん、給料はこんなハイペースで上がらない(ふつうのサラリーマンなら)。
しかも、富を再分配する仕掛け「累進課税」は、資産のリターンは対象外。だから、「働いて稼ぐ=給与所得」は税金面でもハンディがあるわけだ。
事実、ピケティの調査によれば、1950年から2010年までに、資産は25倍に増えたのに(年率5.3%増)、所得は10倍(3.8%増)にしか増えていない(世界の平均)。
とはいえ、サラリーマンをやめて、全財産はたいて、投資に走るのはお薦めできない。投資は損することもあるから。そして、損するのはたいてい生活資金で投資している人。なぜなら、生活費に困れば、損切りするしかないから。一方、金持ちは生活費に困ることはないので、下がったら売らなければいい。つまり、投資先が破綻しない限り損することはないのだ。
ところで、給与所得の伸び率は、実際どれくらいなのか?
日本のサラリーマンの給与所得の推移をグラフで表すと・・・
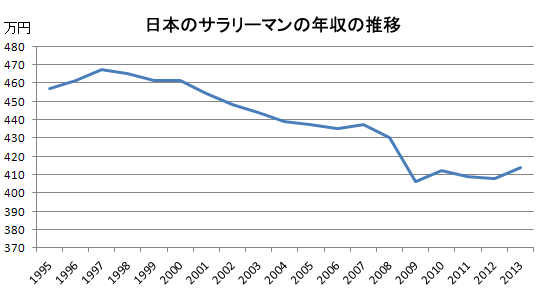
あらら・・・伸び率どころか、20年間、下がりぱなしではないか!
じつは、これには日本の特殊事情がある。1990年台のバブル崩壊が、ノドに突き刺さった小骨にように、今も効いているのだ。
だから?
事情なんかドーデモいいんじゃん、給料が下がり続けていることが問題だろ!
たしかに。
では、つぎに米国の給与所得。
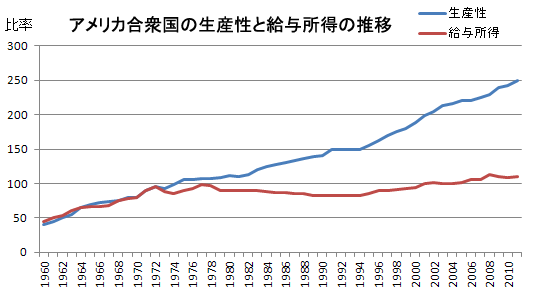
赤い線が給与所得だが、1972年以降、ゼンゼン上がっていない。この間、米国では株価は一本調子で上がっているのに。
つまり・・・
資産の増加率>>給与所得の増加率
はあたりまえ、そして、貧富の差が広がるのもあたりまえ。
ところで・・・
このグラフにはおかしな点がある。「給与所得」のグラフでなく、青い「生産性」のグラフだ。
■給与所得が上がらない理由
グラフをみると、「生産性」は1960年から現在まで一本調子で上がっている。ここでいう「生産性」とは、一人あたりの生産量だ。
たとえば、一人一年で100個生産できたとする。それが、翌年、150個生産できたら、生産性は1.5倍に上がったことになる。当然、「生産性」が高いほど、一人あたりの売り上げも大きい。だから、給料も増えて当然・・・
事実、1972年までは、給与所得は生産性につられて上昇してきた。
ではなぜ、給与所得だけが上がらなくなったのか?
考えられる理由は2つ。
まず、生産性が上がったのは、工場ならロボットとオートメーション、オフィスならIT(最近はITCという)のおかげ。つまり、労働者の能率が上がったわけではないのだ。マシンのおかげで技能が低くてすむなら、むしろ、人件費は下がってもいい?
しかも、ロボットやITの投資額は増える一方。結果、生産コストに占める人件費の比率は低下している。つまり、生産性向上に寄与しているのは、人ではなく、設備なのだ。だから、設備費が上がるのはわかるが、人件費が上がるのはおかしい、その前に利益が減って、会社が破綻したらどうするのだ!
と、経営者や資本家がコーフンするのも、わからないでもない。
もう一つの理由は、会社の利益還元の方法。
まずは・・・
会社は誰のものか?
社員のもの、みんなもの、と言い切る立派な経営者もいるが、現実は株主のもの(法律上)。だから、儲かったぶんは、会社の主(あるじ)である株主に還元するのがスジ。具体的には、配当を増やし、株価が上がるよう努力する。つまり、会社が優先すべきは、配当と株価で、社員の待遇は二の次!というわけだ。
現実に・・・
2015年12月、スプリングアウル・アセット・マネジメント社は、米国ヤフーに対し、全従業員の約8割の人員削減とメイヤー最高経営責任者の退陣を迫った。あっと驚く大胆不敵な要求だが、スプリングアウル社にはその権利がある。ヤフーは業績不振が続いているし、スプリングアウル社はヤフーの株主だからから。つまり、会社は株主のものなのだ。
このような株主優先の傾向は、カジノ資本主義がはじまった1980年以降、顕著になった。働いて稼ぐより、お金を転がして稼ぐ方が手っ取り早い、そんな風潮がアシストしているのだ。つまり、カネ、カネ、カネ・・・
元々、おカネ(貨幣)は取引の手段として発明された。それ以前は、物々交換だったが、取引のたびに等価のモノを用意するのは大変だ。そこで、モノやサービスの価値を一元管理する方法が生まれた。その概念が「価格」で、実体化したものがおカネだったのだ。
ところが、いつの間にか、おカネがおカネを生むようになった。金融資本主義の始まりだ。おカネを貸せば、利息がもらえる。株を買えば配当がつく。株を安値で買って、高値で売ればさらに儲かる。
と、ここまでは良かったのだが・・・
返せる見込みのない人のローンまで金融商品にした結果(サブプライムローン)、100年に一度の金融危機「リーマンショック」を引き起こした。
どこの馬の骨ともわからない者の(失礼)、物騒なローンを金融商品にする?
売る者も売る者なら、買う者も買う者だ。もっとも、それが「ジャンク」だと気づく人はほとんどいなかったのだが。
これを「カジノ資本主義」と言わずして、なんと言うのだろう?
こうして、「価値(モノ・サービス)」と「おカネ」の乖離(かいり)がはじまった。
工場や事務所や店舗を建てて、人を雇用して、モノやサービスを提供する。その売り上げを、給料やボーナスとして労働者に還元する。その余剰金で役員報酬と株主配当を払う。そんな真っ当なヒト・モノ・カネの関係が崩壊しようとしているのだ。
つまり、こういうこと。
給料は労働の対価ではなく、1セントでも切り詰めるべきコスト・・・だから、会社の経営陣は「人件費=給与所得」を極限まで下げ、株の配当や株価をできるだけ上げようとする。彼らの評価はこの一点にかかっているから。
結果、給与所得は上がらず、配当と株価、つまり、資産だけが上がることになる。
だから、ピケティの方程式、
資産の増加率>給与所得の増加率
は自明の理なのだ。もちろん、前者の「資産の増加」にあやかれるのはお金持ちだけ。
つまり・・・
「富める者」と「貧しき者」の格差が拡大するのは必然、「資本主義の大原則」なのである。
では、解決策は?
古きを捨てて、新しいシステムへパラダイムシフトするしかない。そして、今まさに、新しい資本主義が始まろうとしているのだ。
参考文献:
「21世紀の資本」トマ・ピケティ(著),山形浩生(翻訳),守岡桜(翻訳),森本正史(翻訳)出版社:みすず書房
by R.B


