飛行船(1)~球体飛行船と蒸気飛行船~
■謎の球体飛行船
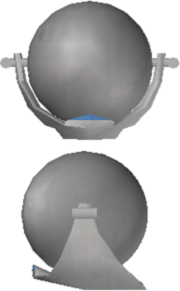 この奇妙なイラストは何か?じつは「飛行船」なのである。それも、模型やラジコンではなく、ホンモノ。上が飛行船の正面図で、下がは側面図である。それにしても、見るからに異形。ジュール・ヴェルヌの小説に出てきそうな夢ふくらむ飛行船だ。
この奇妙なイラストは何か?じつは「飛行船」なのである。それも、模型やラジコンではなく、ホンモノ。上が飛行船の正面図で、下がは側面図である。それにしても、見るからに異形。ジュール・ヴェルヌの小説に出てきそうな夢ふくらむ飛行船だ。
この異形の飛行船を開発したのは、フレデリックファーガソン社長率いるカナダのバンデューゼン社。飛行船の大きさは18階建てビルに相当し、60トンの貨物を運べる(はずだった)。しかも、最高速度は時速120km、航続距離は800kmとスペックもなかなかのもの。
ヘリコプターが積める荷物は15トン程度なので、重量貨物の輸送を一変させる(はずだった)。世界の航空技術者たちも「100年先をいく飛行船」と絶賛したものだった。
この飛行船のユニークな点は、球体を回転させることで浮遊すること。球体を回転させながら、水平移動すると、
「球体の下部の圧力>球体の上部の圧力」
で、飛行船が上昇する。なんのことだかサッパリ。だいたい、球が回転したくらいで、18階建てのビルが宙に浮く?
じつは、インチキでも何でもなく、物理の法則でちゃんと説明できるのである。1783年、スイスの物理学者ベルヌーイが発見したベルヌーイの法則によって。この法則によれば、
「流体が流れる速度が大きいほど、圧力が低下する」
ここでいう流体とは、空気や水のように、どんな形にもなり、「流れる」ことが可能なものをさす。もう少し詳しくみていこう。
イラストの側面図(下の図)で、球体飛行船が左方向に移動するとしよう。このとき、球体が回転していなければ、球体の上部と下部を流れる空気の速度は同じ。これは直感的に理解できる。つぎに、球体が時計方向に回転しつつ、左方向に移動すると、球体の上部の流速は、球体の右回転の速度が加わり、その分速くなる。逆に、球体の下部の流速は、球体の回転速度分だけ減速され、遅くなる。
ということは、
「球体の下部の流速<球体の上部の流速」
そこで、ベルヌーイの法則をあてはめると、
「球体の下部の圧力>球体の上部の圧力」
となり、球体は上下の圧力差で浮き上がる。野球のボールに回転をかけると、球が浮くのと同じ原理。
ベルヌーイの法則は流体の基本法則だが、
「流体中を球(円柱もOK)が回転しながら進むと垂直方向の力が働く」
とより具体化したものを「マグナス効果」とよんでいる。じつは、野球のボールや球体飛行船はマグヌス効果で説明されることが多い。ただし、基本はあくまで「ベルヌーイの法則」。
球体飛行船は水平移動するか、逆に空気が流れていないと、揚力がえられない。球体の上下に流速の差が生じないからである。そこで、球体飛行船は2基のターボプロップエンジンで水平移動して揚力をえる。では、どの程度の回転が必要なのか?毎分5回程度の回転で、飛行船は浮き上がるという。意外に少ないが、球体内部のヘリウムガスの浮力もあるからだろう。
一方、球体飛行船は安全性も高いという。墜落しても球体がバウンドするから(ようわからん)。また、野球のボールが上下左右に曲がるのと同様、球体飛行船も、鋭角ターン、Uターン、垂直離着陸も自由自在、まるでUFO!(ようわからん)。価格は1機10億円もするが、航空事業と割り切れば、決して高くはない。ということで、航空機の歴史に残る大発明!?
ところが、一つ問題がある。球体飛行船が飛んでいるのを誰も見たことがないのだ。TV、映画、書籍でも見かけないし、歴史年表に刻まれた跡もない。では、これって何についた話?
じつは、この球体飛行船は20年前の雑誌の記事(※1)。いろいろ調べてみたが、球体飛行船の「その後の消息」はつかめない。歴史から完全に消されている。技術、運用、経営、どんな問題があったのか知らないが、はっきりしているのは、現在、どこにも飛んでいないこと。
ただ、ルックスはいいし、浮遊原理も”熱い”し、技術者なら興奮せずにはいられない。これほどの発明が「謎の球体飛行船」で終わるのは惜しい。しかし、ものは考えようだ。20年経過しているので、特許料を払う必要はないし、公知の事実なので、今後特許が成立することもない。
最近、ベンチャーといえば、「ハイテク」がすっぽり抜けたITサービス業ばかり。そこで、ベンチャーの原点にもどって「ものづくり」に人生を賭ける人はいないだろうか。もちろん、ターゲットは「球体飛行船」。あの異形の球体飛行船が世界中の空を飛び交う、想像しただけでゾクゾクする。大金を稼げればもちろんハッピーだが、たとえコケても、歴史に名は残る。
たとえば、
・驚異の機械時計を制作したブレゲ(名声のみ)
・夢の世界システムを考案したニコラ・テスラ(完成せず)
・史上初の大陸間弾道ミサイルV2ロケット(兵器としては役立たず)
・異形のコンピュータチューリングマシン(実用化されず)
・史上初めて電気自動車を量産したテスラモーターズ(儲かってない)
・コンピュータの概念を変えたAppleⅡ、iPadのアップル社(一応成功)
どうやら「儲かる儲からない」は、歴史上の知名度とは関係なさそうだ。ということで、誰か「球体飛行船」をやりませんか?
■熱気球
飛行船の歴史は、「空を飛びたい」という人間の欲求からはじまった。古くは、ギリシャ神話のイカロスの翼。もっとも、鳥のようにはばたいて飛ぶ方法は、1600年代には断念されている。イタリアの学者ジョヴァンニ・ボレッリが、鳥と人間では筋肉の相対的な重さが違うため、原理的に不可能と考えたのである。そこで、もっと手っ取り早い方法が採られた。
1783年6月5日、モンゴルフィエ兄弟は無人の気球を飛ばすことに成功する。直径11mの麻布製の気球に、熱した空気を入れると、みごと宙に浮いたのである。これが歴史上初の熱気球となった。じつは、熱気球はお手軽飛行ツールとして今も現役である。
熱気球が空を飛ぶ原理は、たいてい、次のように説明される。冷たい空気より暖かい空気の方が軽いので、気球内部の空気を暖めればその分軽くなり、浮き上がる?だまされたような・・・説明が間違っているわけではないが、これで納得する人は少ないだろう。
たぶん、一番分かりやいのは、物が水に浮く原理。木のように軽い物を、水中に沈めると、浮き上がろうとする。これが浮力だ。ただし、物には重さ(=重力)があるので、
「浮力>重力」
なら浮き、その逆なら沈む。ところで、浮力の大きさはどうやって決まる?有名な「アルキメデスの原理」によれば、
「流体の中の物体は、それがおしのけた流体の重さ(=重力)と同じ大きさの浮力を受ける」
この場合、物体がおしのけた体積分の水の重さが浮力となる。なので、体積が大きいほど、浮力が大きい。ところが、そのぶん、物体の重さも増え、重力も増す。では、どうやったら、浮くのか?
物体の体積を大きくして浮力を増やし、物体を軽くして重力を減らせばいい。
これは、「水中」の「物体」の話だが、そのまま「空気中」の「気球」に置きかえると、、気球を大きく、軽くすれば、浮きやすくなる。気球を軽くするには、気球内部の空気を熱すればいい。空気が膨張し、密度が下がり、結果として軽くなるから。これが、熱気球が浮き上がる原理だ。
■蒸気飛行船
とはいえ、いちいち空気を暖めるのも面倒だ。それに、空気を暖めて軽くするくらいなら、初めから、軽いものを入れればいい。そこで、気球の中に空気より軽い水素やヘリウムを入れるアイデアが生まれた。これが飛行船である。とはいえ、上がったり下がったりでは、何の役にも立たない。水平移動が必要である。そこで、プロペラ推進が考案されたが、問題はエンジン。この時代、まともなエンジンは蒸気機関ぐらいだった。
イギリスのワットは、1769年に蒸気機関を発明したが、これを飛行船に使おうとしたのがジョージ・ケイリーだった。ところが、図面を引いたところで、この世を去る。歴史上初めて、蒸気飛行船を飛ばしたのは、フランスのアンリ・ジファールである。ジファールは、1851年、「飛行船に蒸気を使う特許」を取得したが、ワットほどの名声と富は得られなかった。昔も今も、特許が大金を生むのは、千に一つ、いや万に一つかもしれない。
1852年9月24日、ジファールの蒸気飛行船は歴史上初めて空を飛んだ。この蒸気飛行船は長さが44mあり、彼が設計した自慢の蒸気機関が装備された。重量はボイラーも含め150kgで、軽量化の努力がうかがえる。ところが、出力はたったの3馬力。風が吹いたらおしまい、逆らって進むこともできなかった。面白いのは、この蒸気飛行船には帆がついていたこと。空飛ぶ飛行帆船・・・想像しただけでワクワクする。というわけで、歴史上初の動力飛行は「蒸気飛行船」。
■消えた飛行船の未来
1900年、歴史上初の硬式飛行船「LZ1」が建造された。硬式飛行船とは、軽金属で船体の枠組みをつくり、その中に浮揚用ガス袋を入れたもの。一方、軟式飛行船は、
「船体=ガス袋」
なので、船体が変形しやすく、高速飛行はムリだった。
1928年、ツェッペリン社は「LZ1」を改良し「グラーフ・ツェッペリン号」の開発に成功し、航空事業に乗り出した。その後、事業は大成功し、飛行船は20世紀の「空の覇者」が約束されたかのようにみえた。
ところが、たった一回の事故が、飛行船の未来を打ちくだく。最新鋭のツェッペリン飛行船「ヒンデンブルグ号」が着陸時に大惨事をひきおこしたのである。原因は分かっていないが、たった35秒で、全長245mの巨体が燃えつきたのである。そのときの映像は世界中に配信され、飛行船がいかに危険な乗り物かが、人々の心に刷り込まれた。21世紀につながる飛行船の歴史が35秒で消滅したのである。
参考文献:
(※1)コズモ82サイエンスマガジン1982年5月号
ソ連科学アカデミー編金光不二夫他訳「世界技術史」大月書店
by R.B


